今日まで触れずにきましたが、敬愛してやまない元七二一空桜花隊(神雷部隊)分隊長・新庄浩大尉が、3月21日にお亡くなりになりました。享年90。
3月21日は、神雷部隊初出撃(昭和20年、陸攻隊指揮官野中五郎少佐、桜花隊指揮官三橋謙太郎大尉)の日で、毎年、この日に鎌倉建長寺で神雷部隊の慰霊法要が行われています。
奇しくも、まさにその日を選んだかのようなご最期でした。
思い返せば、日本初の敵機撃墜・生田乃木次さんが、昭和7年2月22日、上海事変で撃墜した米人義勇飛行士ロバート・ショートを弔い続けてちょうど70年目の2月22日に亡くなったり、戦後、皇統護持秘密作戦の指揮官となった元三四三空司令・源田實大佐が、昭和に殉じるように平成元年8月15日に亡くなったとか、大西瀧治郎中将の副官を務めた門司親徳主計少佐が、元号は昭和と平成で違えど、大西中将と同じ「20年8月16日」に亡くなったとか・・・・・・新庄さんにしても、情念なり責任感なりで、寿命を自らコントロールされたのかと思うぐらい不思議な符合です。

本日5月11日、四十九日法要と納骨式に、NPO法人零戦の会より、会長(私)、事務局長、副会長2名の計4名がお招きいただき参列させていただきました。

新庄さんは大正11年生まれ、海兵72期出身、終戦時海軍大尉(23歳)。
戦闘機搭乗員として零戦に搭乗し、七二一空では特攻機「桜花」隊の分隊長を務められました。
戦後は「終戦連絡将校」としての任務にも就き、戦争ではありませんが、昭和26年、国電桜木町駅で電車が炎上、106名もの死者を出した「桜木町事件」の、火災車両唯一の生存者でもありました。
たいへんお心の爽やかな方で、若い人と話すのも大好きで、新庄さんを知るものすべての敬愛をあつめておられました。
ユーモアもあり、またいかにも戦闘機乗りらしく勝気なところがあり、かつて日米の元戦闘機乗りが一堂に会してゴルフコンペをやったとき、
「戦争中、もし俺の前を飛んだら、彼ら(米軍元パイロット)はここにいなかった」
とおっしゃったというエピソードが物語るように、自らの技量には強烈な自負心をお持ちでした。(現に、海兵72期出身の戦闘機搭乗員としては稀なことに、飛行時間1000時間あったとのこと)
おそらく、あと10年早く生まれておられたら、ちょうど志賀淑雄少佐のような腕と人望を兼ね備えた戦闘機隊指揮官として、歴史に名を刻まれたのではないか、と評する人もいます。まったく同感です。



3年前の4月18日、NPO法人零戦の会主催で、「新庄さんを囲む会」を催したことがあります。帝国海軍と縁の深い水交会で、当時の若い特攻隊指揮官の思いや体験談をお話いただくという主旨でした。
また一昨年9月の慰霊祭、懇親会の時には、当時の貴重な写真をスライド投影、ご解説をいただき、そのとき、零戦の翼上に取りつけた写真銃の装備状況がよくわかるとして、零戦機体研究の第一人者Nさんが非常に喜んでおられたのを憶えています。
終戦時、23歳の若い大尉だった新庄さんは、指揮官としての責任ということを常に考えておられるようでした。
NPO法人零戦の会の集いなどで、新庄さんが、
「桜花などは、本来われわれ兵学校出身の士官だけで編制すべきだった。予備学生の人たちも巻き込んでしまったのは痛恨の極み」
・・・・・・とおっしゃるのを、同じく神雷部隊桜花隊におられた予備学生13期・鈴木英男大尉が、
「予備士官を巻き込んだとは何ですか!我々も兵学校に負けずに、『やるぞ!』という気持ちで志願したんだ」
・・・・・・とテーブルを叩いて立ち上がり、食ってかかる、という図も、どちらも生き残ったものとして死んだ戦友に済まないという気持ちがにじみ出ているだけに、印象深いものでした。
その鈴木英男さんが一昨年の大晦日に急逝され、新庄さんもまた、鈴木さんのご逝去をおそらく知らぬ間に病に倒れられたので、もしもあの世があるのなら、今頃、お互いにどうしてここにいるんだと、不思議がられているような気がします。
新庄さんといえば、私にはさらに不思議なご縁が。
私が体を壊して週刊誌の報道の第一線からしばらく身を引いた15年ほど前、ある通信制の写真講座の添削を数年間やったことがありました。
毎週、20人から30人の受講生の作品に講評を付けて返すのですが、その中になんと、新庄さんの作品があったのです。
新庄さんはカメラがご趣味で、大きなコンテストに入選する腕前の持ち主でしたが、それ以来、私のことを、ことあるごとに、
「この人は私の写真の先生だから」
と、持ち上げてくださったものでした。
新庄さんの思い出は尽きません。ほんとうに、忘れ得ぬ我が人生の師だと思っています。
ご冥福をお祈りするばかりです。
元神雷部隊桜花隊分隊長・新庄浩大尉の納骨式に参列しました
七五三のモーニングコート~~私の洋服の原点~~
ルッセル島上空の空中戦(70年前の今日)
以下、拙著『零戦隊長~二〇四空飛行隊長宮野善治郎の生涯』より抜粋
〈五月十三日、このところ増強いちじるしいルッセル島の敵航空兵力を叩くため、ひさびさの航空撃滅戦が行われることになった。二〇四空宮野大尉以下二十四機はラバウルからブインに進出、そこで五八二空野口中尉以下十八機と合同して午前八時十五分、出撃した。
総指揮官は宮野大尉、その右後方、三番機には大原二飛曹がついている。高度をとって定針すると、おのおのが照準器のスイッチを入れる。眼前の四角いハーフミラーのガラスに、オレンジ色の照準環の光像が浮かび上がる。計器板上端の左右にむき出しになっている七ミリ七機銃のレバーを操作し、弾丸を全装填、二十ミリ機銃のスイッチを入れる。スロットル先端の切替レバーで七ミリ七だけが発射するようにしておいて、指揮官に従って試射をする。
編隊は高度八千メートルで戦闘体勢を整えながら、十時四十分、ルッセル島上空に突入。間もなく敵機発見、宮野は編隊の誘導を始めた。その途中、大原は、五分先行した五八二空の零戦一機が、F4Uコルセアに追尾されて煙を吐いているのを発見した。
「急いで宮野大尉の横に出てそれを知らせると、隊長は『お前、行け』と手信号の合図を送ってきました。びっくりして『一人でか?』と聞くと、『そうだ。一人で行け』
なんて冷たい隊長だと思いましたが(笑)、編隊を誘導しなければならない宮野大尉とすれば、一緒に来るわけにもいかないし、悲痛な命令であったと思います。
右旋回で七千メートルまで降下し、零戦を追うのに夢中になっているF4Uを捕捉、これを撃墜しましたが、その時、死角になっている左の腹の下からいきなりダダダーッと撃たれたんです。右翼から座席の後ろにかけて被弾、右翼燃料タンクから火を噴きました。ところが、幸か不幸か、穴が大きすぎてかえってガソリンがすぐに燃え尽きてしまい、火は間もなく消えました。
右に逃げると追随されるので左に切り返しましたが、そのままぐるぐる四千メートルまで墜落状態で墜ちていきました。堕ちながら、真下にルッセルの敵飛行場が見えた時には、一瞬、もう駄目かと思いましたが、おふくろさんの顔も、誰の顔も、浮かんではきませんでした。“まだまだ、まだまだ。やられてたまるか”そう思いながら、何とか姿勢を回復しました。
すると今度は、強い力で左上昇旋回しようとする。これは被弾で、昇降舵の連動桿がよじれてしまっていたためだったんですが、それをだましだまし、帰投方向へ機首を向けました。操縦桿を右に倒さないと水平飛行ができませんでした。
しばらく飛んだ頃、ふと後ろを見ると、コルセアが右に二機、左に一機、ピタッとついてきました。送り狼、というやつです。
これは左に逃げるしかない。初弾が当たったら仕方がないと思って、気づかないふりをしてフットバーを踏んで機体を滑らせながら、敵が撃ちだした時、目もくらむばかりの垂直旋回をうちました。一回、二回、回っていると、左にいた一機がスッと目の前に出てきました。そいつに一撃をかけ、撃墜して後ろをふり返ると、もう一機のコルセアがパアッと火を噴くのが見えました」(大原二飛曹談)
五八二空の零戦が一機、救援に駆けつけてくれたのである。一対三があっという間に二対一になり、残りの一機は急降下で逃げてしまった。
コロンバンガラ島に不時着、燃料補給の上帰投したが、被弾は三十八発にもおよんでいた。右翼の燃料タンクは下が見えるほど、バラバラのような状態に穴が開いており、ただでさえ左に傾くのに左翼の燃料タンクをいっぱいにしたので、離陸した瞬間、グラリと左に傾いた。操縦桿を右に倒して姿勢を取り戻し、操縦桿を左手に持ち換えて、右手で脚上げの操作をする。必死の操縦であった。
やっとの思いでラバウル基地にたどり着くと、宮野が待っていた。
「最初の一機を墜とすところまでは見ていた。よくそんなので帰ってこれたなあ」
玉井副長も、
「大原、これは名誉なもんだ。司令に言って靖国神社に飾ってもらおう、一機まるごと持っていくのは大変だから、尾部だけでも内地に送るようにしよう」
と、感心しきりであった。この飛行機がその後どうなったかは、大原は知らない。
この日、二〇四、五八二両部隊は、合わせて約六十機の敵戦闘機と交戦、二〇四空では、宮野大尉・F4U一機(協同)、大原二飛曹・F4U二機、尾関上飛曹・F4U一機(協同)、小林友一二飛曹・P-39一機(不確実)、辻野上上飛曹・F4U一機(不確実)、中村二飛曹・F4U二機、橋本久英二飛曹・F4F一機、黒澤清一二飛曹・F4U三機(うち不確実一)、F4F一機(不確実)、渡辺秀夫上飛曹・F4U二機、P-39一機(不確実)、川岸次雄二飛曹・F4U一機、坂野隆雄二飛曹・F4U三機(うち不確実一)、中澤二飛曹・F4U二機(うち協同一)、鈴木博一飛曹・F4U二機(うち不確実一)、白川俊久二飛曹・F4U二機(うち協同一)、計延べ二十六機もの撃墜(うち不確実七)戦果を報じた。
二〇四空の未帰還者は、野田隼人飛曹長、刈谷勇亀二飛曹の二機で、大原機をはじめ三機が被弾した。野田飛曹長は乙四期、二〇四空きってのベテランで、前年十二月に着任して以来、主に中隊長として出撃を重ね、二機の撃墜を記録していた。刈谷二飛曹は丙二期、四月三日に着任したばかりの搭乗員であった。
「私はその日は搭乗割に入っておらず、悔しい思いをした。(出撃した搭乗員が)帰ってくると、自慢話や未帰還機の状況の話などが出た。未帰還機が出ると遺品整理をやった。でも、戦死者が出たからといって打ちひしがれた気持は全然なかった。お互い様だ、まあ、遅かれ早かれと・・・いうことで。その晩、宿舎には、士官も来て宴会になった」(八木二飛曹回想)
五八二空も、十一機(うち不確実三)の撃墜を報じ、佐々木正吾二飛曹(丙四期)が未帰還、ほか二機が被弾している。五八二空明慶幡五郎二飛曹も、大原二飛曹と同様、燃料タンクに被弾、火焔と黒煙を噴き出して一時は自爆と認められたが、墜落中、奇跡的に火が消え、ムンダで燃料補給の上帰ってきている。
海軍功績調査部のこの空戦に対する行動評点は、二〇四空がA、五八二空はBとなっている。また、大原二飛曹の奮闘に対し、のちに杉本司令より特別善行章一線が付与された。〉
「信楽高原鉄道事故から22年」と「プレスドライバー」
22年前の今日、信楽高原鉄道で列車正面衝突事故が起き、42名が死亡、614名が重傷を負う大惨事となった。
1991年(平成3年)。私は講談社『フライデー』専属カメラマンを勤めていたが、89年から92年までは大阪駐在として名古屋から九州までのニュースを担当していて、その時期のことだった。
ちょうど、大手商社イトマンを舞台にした巨大経済事件「イトマン事件」の渦中で、私は毎日、朝6時にタクシー(さくらタクシーの平良さん。年齢は私より一回り上。日本一のプレスドライバーである)が迎えに来て、大阪地検前に張り付いて捜査状況というか、人の動きに変化はないか見届け、そこに昼までいて、別の取材現場に行くような日々だった。
まだ携帯電話がなくショルダーホンの時代、さくらタクシーは、保有する黒塗りの200数十台のタクシー全車に自動車電話を日本のタクシー会社でははじめて備えて、マスコミ各社の御用達になっていた。
ただ、取材の同行には守秘義務も生じるため、メディアごとに別のドライバーが担当するのがつねであった。
ドライバーの平良さんとは多くの修羅場をともにしていただいた。のちに阪神淡路大震災のとき、私が被災地でほかのカメラマンより動きがとれたのは、平良さんのおかげである。
平良さんは、私の取材のため、自費で車載テレビをつけてくれていた。91年5月14日。いつものように大阪地検前で張り込んでいると、午前11時頃、車載テレビにニュース速報が出た。
「信楽高原鉄道で列車事故。死傷者が出た模様」
ん?列車が衝突事故とはどういうこっちゃ。
とりあえずフライデー編集部に電話で一報を入れる。
すると、まだデスククラスの編集者は一人も出社しておらず、若い編集者はピンとこないのか、
「デスクと相談してまた連絡します」
だが、続報では、「死傷者多数」となっている。ここで平良さんが、
「神立さん、編集部の指示待ってたら出遅れまっせ。これは大事になってると思う。行ってみてもし、たいした事故じゃなかったらタクシー代いらんさかいに、とりあえず行きまひょ」
と言ってくれた。
滋賀県の現場までは、片道3万円近くはかかるが、「いらん」と言われても、そういうわけにはいかない。私も覚悟を決めた。
「すみません、ではお願いします」
「よっしゃ行くでぇ、しっかりつかまっときや!」
平良さんは言うと、猛烈な運転で名阪高速を飛ばし、栗東ICを降りた。
ちょうどそこに、現場へ向かうとおぼしきパトカーや救急車が列を成して走ってゆく。平良さんは、
「これについていったら、現場へ行けまっしゃろ」
と、パトカーの後ろにピタッとついた。
そのまま、赤信号もなにも、パトカーと一緒に突破。
パトカーの警官が後ろを振り返るが、取り締まっているヒマはない。
私は講談社の社旗をフロントガラス越しに見えるようにかかげ、次に取材腕章と記者章を窓から大きく振って見せた。警官は、苦笑いしてうなずいてくれた。
こうして、私は、新聞社のヘリコプターをのぞけば、どこよりも早く、現場に着くことができた。
着いてみると、木々の間から、巨大な芋虫のような金属のカタマリが見えた。列車がつぶれて、前部を持ち上げ、互いにめり込んだ状態でひしゃげているのだ。
驚いた。そうか、列車というのは、衝突安全のことなんか考慮してつくられてないんだな、と思った。
木を伐採し、クレーン車が車内に閉じ込められた人や遺体を毛布にくるんで持ち上げ、救出作業が進む。
ふと、救急隊員の声が耳に入った。
「下半身がはさまっていて取り出せません。もう亡くなってます」
「よし、では切断するしかないな」
やがて、報道各社が集まってくる。救出作業は暗くなるまで続いた。
そして、遺体安置所が近くの学校体育館に設けられたというので行ってみると、40を越す棺が二列に並べられ、駆けつけた家族が、身を寄せ合いながらひとつ、ひとつの棺を見てまわる。
そして、変わり果てた家族の遺体を見つけると、その場で泣き崩れる。
どんな状況でも撮るのがわれわれの仕事だから、私は気をふりしぼってシャッターを切り続けた。
ここで、とても嫌な場面に出くわした。
体育館二階から撮っていると、遅れてきた新聞社のカメラマンが、
「すごいですねえ、死体がいっぱいですねえ、興奮しますねぇ」
・・・・・・と言いながら、嬉々としてカメラを向けているのだ。
「ちょっと待てよ、お前。いくらなんでも不謹慎やろ。場をわきまえろ」
胸倉をつかんで私が言うと、彼はおとなしくなった。彼の腕章には『○○新聞』とあった。
以後、私はこの新聞社の新聞はいっさい取らない。
事故が起きたのは火曜日だった。フライデーの校了日は水曜だから、フィルムを送っていては間に合わない。午前4時、取材を切り上げると、私は、京都駅までタクシーで送ってもらい、そこから始発の新幹線で東京へ。護国寺の講談社の暗室に直行した。
ただ、私も冷静さをいささか欠いていたように思える。
私としては、ご遺族のご遺体との対面シーンの衝撃と印象が強くて、当然そこの写真が使われると思っていたら、編集長が選んだのは、最初に撮ったへしゃげた列車の写真だった。
そのとき、私は大いに不満に感じたが、その数年後、フライデー創刊10周年記念写真展が池袋西武であったとき、展示されたこの写真を見て、ああそうか、なるほど、時代を切り取るのなら、やはりこの現場写真のほうが訴えるものが大きいな、と納得したものである。
その後、信楽高原鉄道と、相互乗り入れで衝突したJR西日本との泥仕合には、あえて触れまい。
この年、立て続けに大きな事件が、私の縄張りで起きた。信楽高原鉄道事故からほどなく、広島で建設中の高速道路が側道に落下、信号待ちをしていた車を押しつぶし、多数の死傷者が出た。翌月、雲仙普賢岳の大火砕流で、報道陣や地元のタクシー運転手ら43人が犠牲になる。
普賢岳のときは私は一本の電話に救われ命拾いしたのだが、ここで殉職した現場仲間のカメラマンの、当時生まれたばかりの女の赤ちゃんが、なんという偶然か、いま私が講義を受け持つ大学にいて、昨季、私の授業を受けている。
そして、ずっと追っていたイトマン事件も、当時の経営者らが逮捕され、一応幕を閉じる。
イトマン事件の取材で、平良さんの車で張り込みをしていた当時、こんなことがあった。
イトマン事件の捜査指揮のため、新たに着任したDという検事正の写真を撮るよう、編集部から要請されたが、このDという人、やり手だが権力をかさに着るタイプで、大の取材嫌いである。
それで私は、たまたま、同じように張り込んでいたライバル誌(現存)のHというカメラマンに、
「僕、D検事正を撮るんやけど、この人が事件を解決するキーマンやから、撮っておいたほうがいいですよ」
と声をかけた。確か月曜日のことで、一緒に撮っても、発売日の関係で先を越されることはない。
やがて、D検事正が専用車で現れる。私は、「Dさん、お願いします!」と叫び、シャッターを切る。Hカメラマンも撮る。
おや、D検事正が「撮るな!」と怒鳴ってるぞ。怒ってるな、じゃあずらかろう。
私は、サッと車に乗り込んで、知らん振りを決め込んだ。
逃げ遅れたHカメラマンは・・・・・・かわいそうに、D検事正に怒鳴られまくり、名刺まで取り上げられている。それを見ながら私と平良さんは大笑い。
そのHさんも、40代の若さで亡くなった。互いに騙したり騙されたりのライバル関係だったが、報道写真のグループ展を一緒にやったこともあった。ちょっと、イタズラが過ぎたかな、といまは反省している。
平良さんは、こういう他社の記者、カメラマンからは、
「神立を乗せてる運転手は、取材もできるらしい」
と、恐れられていた。
事実、なにか事件があって、こちらが現場をつかみあぐねているとき、平良さんは、ほかのマスコミ車の運転手に自動車電話で電話をかけ、
「いま、どこにおるの?」
とさりげなく聞き出してくれる。それでいて、こちらの居所や機密事項は絶対に漏らさない。
阪神淡路大震災のときも、電話がなかなか通じないなか、自らも被災したのに、
「神立さんが絶対くるから、俺、行くわ」
と奥さんに言い残して、伊丹空港到着出口で待っていてくれた。
義理人情に厚く、92年、私が東京に戻るときには、ドライバー一同でお金を出し合って、イギリス・ビリンガムのカメラバッグをプレゼントしてくれた。95年の阪神淡路大震災取材のとき、私が持っていたのがそのバッグである。
いまもときどき、葉書や電話のやりとりがあるが、
「あの頃がいちばん、スリリングで充実してましたなあ」
と言ってくれる。
忘れられない大恩人の一人である。
アーカイブス 『祖父たちの零戦』講談社文庫化にあたって、単行本刊行時を振り返る1
『祖父たちの零戦』が文庫化され、明日、5月15日発売になる。
文庫発売にあたって、3年前の単行本発売の頃を振り返ってみる。
新著「祖父たちの零戦」講談社ウェブサイトに!
テーマ:『祖父たちの零戦』講談社刊
新著「祖父たちの零戦」、版元の講談社ウェブサイトの新刊ページにも掲載された。
http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2163020&x=B
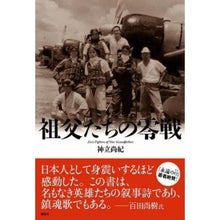
ソフタチノゼロセン
祖父たちの零戦
著者: 神立尚紀
発行年月日:2010/07/20
サイズ:四六判
ページ数:408
ISBN:978-4-06-216302-6
定価(税込):1,890円
--------------------------------------------------------------------------------
内容紹介
--------------------------------------------------------------------------------
『永遠の0(ゼロ)』著者絶賛!
日本人として身震いするほど感動した。この書は、名もなき英雄たちの叙事詩であり、鎮魂歌でもある。――百田尚樹氏
「この戦争が正しいかどうか、そんなのは後世の歴史家が判断することだ。国のため、天皇陛下のため、家族を守るため、そんな観念的なことは論じなくていい。われわれは、敵に勝つためだけに訓練を行う。空戦になれば、向かってくる敵機を叩き墜とす、それだけを考えろ。目の前の敵機との戦いに全力を尽くせ。戦争は、始まった以上は勝つしかないからな」――<本文より>
昨日あたりから、講談社が見本本(市販本とまったく同じ)を各メディアや関係者に発送を始めているらしく、
「本が届いた」
という電話がジャンジャン鳴る。
いまさっきは、取材でものすごくお世話になった元海軍造兵大尉(技術短現一期)で中島飛行機のエンジン技術者を経て戦後プリンス自動車に入った風見さん(戦前の内閣書記官長・風見章氏の長男、94歳)、そしてキングレコードで、この本の主人公の一人である鈴木實氏の部下としてカーペンターズを世に出した粟飯原さんから。
零戦の本で、技術者はともかく、歌手や搭乗員の戦後の勤務先の部下にまでインタビューしたものはほかにないと思う。
というわけで、重ねてどうぞ宜しくお願いいたします。
Amazonは便利だが、くれぐれも「中古」ではなく新本をお買い上げいただけますよう。
今日はみたま祭りの靖国神社で、硫黄島で壊滅した二五二空舟木部隊の慰霊昇殿参拝をしてきた。角田和男さんの代参。角田さんの四番機だった勝又兵曹の弟さんほかご遺族の方々とご一緒する。
昼食は、T事務局長、U事務局次長と靖国神社南門前、海上自衛隊Ⅰ2佐御用達の店で魚の旨い「宮」へ。ムツ照焼き定食、驚くほど美味。市ヶ谷まで戻ったところで、カメラバッグを店に置き忘れたことに気づき、あわてて戻る。
またやってしまった。時価数十万円から数百万円の機材が入ったカメラバッグをどこか(電車の中、高速PAのトイレ、デパートのトイレ、洋服屋の試着室、高速バスの荷物室の中などなど)に置き忘れたというのは学生時代から覚えているだけでも10回はある(車で出かけたことを忘れて歩いて帰ったこともある)が、不思議とモノがなくなってしまったことはない。日本はいい国だと思うのはこんなときだ。
アーカイブス 『祖父たちの零戦』講談社文庫化にあたって、単行本刊行時を振り返る2
『祖父たちの零戦』が文庫化され、明日、5月15日発売になる。
文庫発売にあたって、3年前の単行本発売の頃を振り返ってみる。その2。
「祖父たちの零戦」(講談社)いよいよ発売。取材に協力いただいた方からの反響
テーマ:『祖父たちの零戦』講談社刊
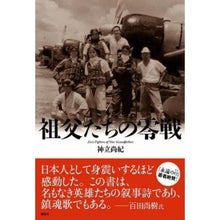
「祖父たちの零戦」、いよいよ今週から書店に並ぶ。
あらかじめ、取材でお世話になった人や関係者には本をお送りしている。
それでここ数日、本が届いたという電話、メールが次々と。
いつも思うが、こういうときは不思議と年齢の上の人から順に電話がかかってくる。年長者ほどレスポンスが早いのだ。94歳の風見博太郎さん(造兵大尉、中島飛行機)、91歳の木名瀬信也さん(大尉)、89歳の加藤清さん(飛曹長)・・・・・・。
特攻筑波隊の指揮官だった木名瀬さんは、
「いままで出したあなたの本の中ではいちばんいいんでないの?」
とおっしゃる。
加藤さんは新潟県某市で、地元で一番大きな建設会社を経営している。かつては零戦の名パイロットで、主にインドネシア、オーストラリア上空で敵機32機を撃墜破したという、航空隊司令から出された表彰状が残っている(うち、撃墜したのは23機だそうだ)。「祖父たちの零戦」のなかでも、重要な場面で幾度か登場する。
気風がよく大好きな人だが、長いことご無沙汰してしまっていた。その加藤さんから、懐かしさのこもった元気な声で、
「がんばってるね!忙しいだろうけど時間作って、また遊びにきてよ。顔も見たいし」
と言われ、思わず涙が出る。
また、主人公の一人、鈴木實中佐の奥さんからお電話。
「何が書かれているか、もう怖くて。ドキドキしながら寝ずに読みました」
とのこと。20冊ご注文くださるとか。10月、東京に来られるのでそのときの再会を約束する(きっとその前に私が広島に会いに行くと思うけど)。まったく、息子のようにかわいがってくださる。
ご子息・盾行さんからも電話。
「おやじは自分のことを全然、語らなかったから。初めて知る話がいっぱいありますよ。孫にもぜひ読ませたい」
と、5冊の注文をいただく。かなりプライバシーに触れる内容にも、
「全部事実ですから、一向に気になりません」
と。ちょっとホッとする。
光人社出版部長の坂梨さん(これまでに光人社から出した私の本をすべて担当してくださった)にはこちらから電話。坂梨さんは今回、よその会社(講談社)からの出版であるにもかかわらず、いろいろと尽力くださった。なんと御礼を言っていいか。
坂梨さんが、
「ひとつ神立さんに謝らないといけないことがあるんです」
という。
「えッ、なんですか?僕、なんかされましたっけ?」
「ウチの会長が5月に亡くなって、それを知らせてなかったので・・・・・・」
「・・・・・・!」(絶句)
光人社会長・高城肇氏。享年82。亡くなったことは故人の遺志でこれまで伏せられていたという。
高城氏は、「大空のサムライ」「サムライ零戦記者」「奇跡の雷撃隊」その他、昭和40年代、50年代の戦記ブームの頃、戦争体験者の名前で出された戦記本の多くを執筆し、自身の名前でも「六機の護衛戦闘機」「非情の空」といった名作を書いた伝説的な天才編集者だ。
これまで出した私の本にも目を通してくださり、九段の光人社でよく「がんばれよ!」と声をかけてもらったものだ。「零戦隊長」を書いたときは、「よくやった」と、手を握ってくださった。
今年1月、新著のために改めてお願いした私のインタビューに5時間も応えてくださり、坂井三郎さんの名前で出してベストセラーになった「大空のサムライ」を高城氏が書くにいたった経緯などをこと細かにうかがった。そのときは、
「こんな話、いままで興味を持って聞いてくれる人は一人もいなかったよ」
と、終始上機嫌で、饒舌に話をしてくださり、
「またいつでも話するから。気軽にいらっしゃい」
と言ってくださったのだが・・・・・・。
2月に倒れ、そのまま会社に出ることもなく亡くなったと。
いま思えば、ご自身の遺言を残そうとされていたのでは・・・・・・というのが、私と坂梨さんの見立てである。
その高城氏の「最後の証言」は、「祖父たちの零戦」のなかで書かせていただいている。
ご縁というのか、無常というのか、言うべき言葉も見当たらない。
高城氏のご冥福をお祈りいたします。
大原亮治さん(飛曹長)から電話あり。大原さんは前著「零戦隊長」の副主人公だ。
「しかしあなたもよく書くなあ」
といわれる。本の中身に関連して貴重なエピソードをうかがう。が、このところ元気なくちょっと心配。
推薦のお言葉をいただいた阿川弘之先生より携帯にお電話。
「本ができておめでとうございます。夢中で読ませていただいてます。評判になるといいですね」
とのお言葉に胸がいっぱいになる。
この物語の登場人物の一人でもある女優・森光子さんに「祖父たちの零戦」をお送りしたところ、なんと、届いた翌日にお礼状をいただいた。
すごい!早い!
やはり、年長の方、社会的に知名度のある方ほど律儀でこういうことにはきっちりしていらっしゃる、ような気がする。
昨年、フジテレビの「放浪記」2000回記念番組で、私も写真提供で少しだけお手伝いしたが、森光子さんは昭和18年秋、主人公の鈴木實少佐率いる二〇二空零戦隊のいた蘭印セレベス島(現・インドネシア・スラウェシ島)ケンダリー基地に、慰問団の歌手の一人として行かれている。慰問演芸会の翌日、零戦隊の出撃があり、そのとき出撃を見送った森光子さんに、手作りのマスコット人形を飛行服のベルトに挿してもらった搭乗員がご存命で、本にはそのエピソードも出てくる。
沖縄戦のくだりで登場する元零戦搭乗員の土方敏夫さん(大尉)よりお電話。来週火曜にご自宅にうかがうことになる。
NPO法人零戦の会・岩下会長(大尉)からもお電話。最近入院されたとか。心配である。
岩下さんによると、私と同年代で「零戦の会」米国支部長の、NASAのエンジニア、マイケル・フレッチャー氏が先日、カリフォルニアから鎌倉に来たらしい。
マイクさんは9月にも東京に来て会う予定になっている。9年前、ハワイで会って以来、年に2度は会っているので、外国人のような気がしない。奥さんは美人の大阪人、日米ハーフのかわいい二人の子どもがいる。
年中、日本に来ているような気がして、この人はいったいいつ仕事してるんだろうか、NASAの技術者はヒマなのか、と不思議な気がする。聞けば、かなりの予算を動かせるポストにいるらしいが、彼の仕事している姿を見たことがないので、半信半疑(笑)である。もっとも、それはお互いさまで、いつも会うたび、握手しながら、
「チャント仕事シテマスカ?」
「あんたこそ、いったいいつ仕事しとんの?」
と言い合うのが挨拶の第一声になっている。
真珠湾攻撃「加賀」雷撃隊の吉野治男さん(少尉)からもお電話。本が出たことをとても喜んでくださった。近年三度も大きな手術を受け、体調が思わしくないらしく、
「私も気がつけばもう90歳だからびっくりしますよ。仲間のほとんどが戦死してるのに、この年になるまで生きてるのが不思議な気がしてしようがない」
とのこと。
「しかし、ずっと寝たきりってわけではないし、また折を見て会いましょう」
と言ってくださり、再会を約す。進藤三郎さんのことは、
「あの人は艦隊で有名だったからよく知ってますよ」
とおっしゃっていた。
一冊の本に込められた人との出会いの多さと深さは、自分でも驚くほどだ。この本にこめられた「思い」の総量と、私を導き、この本を書かせてくださった人々の「縁」の不思議さを思うと、襟を正さざるを得ない。無我夢中で書いた苦しみは消えて、感謝の気持ちで発売日を迎えられることを幸せに思う。
今年は、零式艦上戦闘機が海軍に制式採用(昭和15年7月24日)されてちょうど70年の節目の年だが、主人公の一人、鈴木實さん生誕100年でもある。(もう一人の進藤三郎さんは来年が生誕100年)
本には書いていないことだが、鈴木さんが亡くなる半月前の平成13年10月上旬、私は三原に、全身麻痺で寝たきりの鈴木さんを見舞い、お風呂に入るのをお手伝いした。
帰り際に私は、
「鈴木さんが100歳になられたら、また本を出しますから、それまで頑張って長生きなさってください」
と言ったが、鈴木さんの
「100歳か・・・・・・あと9年は長いなあ」
との嘆息に、しまった、かえって酷なことを申し上げたかと悔やんだのを鮮やかに覚えている。
だが今回、期せずして、その約束を果たすことができたのだ。
才うすき私にチャンスをくださり、終始、叱咤激励し、血の通った丁寧な編集をしてくださった講談社学芸図書出版部長・加藤晴之氏、的確なページ構成をしてくださったミシマ社の大越裕氏、この上ないカッコいい装丁、本文デザインを手がけてくださったデザイナーの加藤愛子さん(なんとガダルカナルにも旅したことがあるという)に、本の中で謝辞を述べられなかったので、この場を借りて心より御礼申し上げます。
感無量で書く手が止まらないので、今回はこれにて。
よろしくお願いいたします!書店で見つけたら、ぜひ迷わずレジへGO!Amazonなら新本を!
アーカイブス 『祖父たちの零戦』講談社文庫化にあたって、単行本刊行時を振り返る3
『祖父たちの零戦』が文庫化され、明日、5月15日発売になる。
文庫発売にあたって、3年前の単行本発売の頃を振り返ってみる。その3。
20歳から93歳まで
テーマ:『祖父たちの零戦』講談社刊
朝、岩手県の三上一禧さん(少尉)からお電話。三上さんは93歳、ちょうど70年前の「零戦」の初の空戦に参加した13名の搭乗員のうち、現在ただ一人の生き残りだ。新著「祖父たちの零戦」(講談社)でも、試作機のテストや最高速試験、高高度実験、初空戦、自分が撃墜した敵パイロットとの戦後の再会など、重要な局面でご登場いただいている。
「本、届いたよ。いやー、ありがとう。9月に東京で会えるのを楽しみに、節制して体調を整えてますよ」
三上さんとはしょっちゅう話すが、70年前の当事者と、こんなふうに電話で話せるというのは、じつは大変なことだ。朝からかなり元気をもらう。
で、学校へ。学校に着いたら携帯に留守番電話。宮崎勇さん(少尉)からだ。宮崎さんも、グラマンF6Fとの対決など重要な場面の登場人物だ。宮崎さんは91歳。
「大阪の宮崎勇です。声が聞きたくてかけました。また電話します」
コールバックするがつながらず、ちょっと心配。
授業が始まる前、前作「零戦隊長」で大変お世話になった、故・宮野善治郎大尉の甥、善靖さんと電話で話す。
なんと、奥さんが61歳で亡くなったという。
奥さんはとても快活な方で、はじめてお会いしてから10数年、私もよく励ましていただいた。肺癌だったらしいが、大ショックである。動揺を引きずったまま、授業。
帰宅するとすぐ、日高盛康さん(少佐)の訃報が。日高さんは男爵家の生まれ、歴戦の零戦隊指揮官で、戦後は航空自衛隊から富士重工のテストパイロットを務めた方だが、戦後一切、自らの戦争体験について口を閉ざしていた。
日高さんが、ジャーナリストのインタビューに応え、戦争体験の一部始終を語ったのは、私と渡辺洋二さんに対してだけである。
光人社の会長室を借りて、はじめてお会いいただいたときの緊張と感激、これまで黙して語られなかった歴史の機微を、いままさに私が聴いているという不思議な感覚は忘れられない。
不思議と、私には心を開いてくださり、多いときは月に一度は靖国神社で会ったし、日高さん、土方敏夫さん(大尉)、渡辺洋二さん、私の4人でよく、「新宿中村屋でカレーを食う会」「美々卯でうどんすきを食う会」をやった。日高さんはいつも、戦死した列機搭乗員の写真をカバンに忍ばせておられた。
最後にお会いしたのは1年半前。
別れ際、ふと「これが最後かも」という予感がして、涙が出たのを覚えている。その頃、何度かに分けて、日高さんが手元に残していたお宝級の資料を、「もらってください」と、宅急便で送ってこられた。日高さんも、残り時間があとわずかであることを感じておられたのだろうか。
92歳、いわゆる御歳に不足はないとはいえ、日高さんの笑顔が二度と見られないのかと思うと、胸が締めつけられるように痛み、涙がとまらない。
本物の華族(貴族)だから当然だが、本当にノーブルというか気品のある、カッコいい方だった。
夜、O元一飛曹と電話で話す。Oさんも壮絶な戦争体験をしてきた方だが、戦後は長く刑事を務め、二年前、これも壮絶な介護の末、奥さんを亡くしている。
そのOさんが、「出版祝」を贈ってくださったのだ。
86歳のOさんは、最近、ゲートボール仲間で一歳下の彼女ができたとかで、うれしそうだ。人間、いくつになっても恋はできるし、するべきだと思う。明るいOさんの声を聞いていると、なんだかホッとする。
しかし、考えてみると、一日の間に20歳(学生)から93歳までの人と会話を交わす、というのはすごいことなのかもしれない。
PR: 今までにない部屋探しサイト「Nomad.(ノマド)」
『祖父たちの零戦』神立尚紀著(講談社文庫)明日5月15日発売です。

みなさま、どうぞよろしくお願い致します。
※お一人様何冊でもOKです。
握手券はついていませんが、ご購入くださった方には握手もサインも喜んでさせていただきます。
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2775301&x=B
大空を翔けた零戦飛行隊長のドキュメンタリー
この書は、一代の名機「零戦」に跨り、日本のために命を懸けて戦った、そんな名もなき男たちの鎮魂の書である――百田尚樹氏
ミノル、俺たちのやりたかったことはこんなことだったのかな――二十七機撃墜・味方損失ゼロ、奇跡の初空戦を指揮した進藤三郎。敗色濃い南太平洋でなおも完勝を続けた鈴木實。二人の飛行隊長の人生を縦糸に、元搭乗員一二四名への二〇〇〇時間インタビューを横糸に織り上げた、畢生(ひっせい)のノンフィクション!
※本書は2010年7月に講談社より刊行されました。文庫化にあたり、一部を加筆・修正しました。
http://www.amazon.co.jp/祖父たちの零戦-Zero-Fighters-Grandfathers-講談社文庫/dp/4062775301/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1368091620&sr=8-2&keywords=祖父たちの零戦
- 祖父たちの零戦 Zero Fighters of Our Grandfathers (講談社文庫)/講談社
![]()
- ¥830
- Amazon.co.jp
『切腹の日本史』大野敏明著(じっぴコンパクト新書)
いつもながら目の付けどころが鋭くて、文章にキレがあり読みやす
この本も、お薦めです!
『切腹の日本史』大野敏明著 (じっぴコンパクト新書)
内容紹介
日本にしかみられない責任の取り方としての切腹は、武士の究極の
鎌倉時代にはじまり、戦国期の武士のならいとして定着してきた身
戦に敗れた者は首級を取られる前に潔く腹を切り、自害して果てた
江戸時代には、刑罰として罪を償うために、またあらぬ不名誉な汚
主君に抗議しての諌死や、後を追っての殉死での切腹もまた日本人
歴史に刻まれた武士道の振る舞いの、背景とその真情に迫る。
松平信康、千利休、古田織部、豊臣秀次、浅野長矩、大石内蔵助、
松平康英、渡辺崋山、新見錦、新選組、真木和泉、、武市半平太、
西郷隆盛、乃木希典、河野寿、中野正剛、三島由紀夫、森田必勝、
・・・・・・国民を欺き国を誤った民主党議員、前議員の皆さんにもぜひお薦めしたい一冊です。
内容(「BOOK」データベースより)
不始末の責任をとり、あらぬ汚名をそそぎ、あるいは義憤からの諌

講談社文庫の月刊情報誌「IN POCKET」の「もうひとつのあとがき」(『祖父たちの零戦』)
講談社文庫の月刊情報誌「IN POCKET」の「もうひとつのあとがき」の中で、15日に発売された拙著『祖父たちの零戦』に関連して「ラバウルにて」と題する一文を寄稿しています。
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bunko/pocket/index.html
『祖父たちの零戦』講談社文庫版、おかげ様にて発売初日の午前中から、Amazonで品切れになり、ご不便をおかけしております。
品薄はすぐに解消するはずですので、今しばらくお待ちいただければ幸いです。
操練出身搭乗員のエピソードに想う。
それでも大戦中期ぐらいまでの士官の場合は数も少なく、人事も海軍省の所管だから、ハンモックナンバーや経歴を調べることは比較的容易だが(それでも、鴛淵孝大尉が中尉時代に台南空にいたなどと適当なことを書く人もいる)、特准、下士官兵の場合は人数も多いし、各鎮守府ごとの話になるのでややこしい。
搭乗員の場合、予科練出身者なら、甲飛会、雄飛会(乙飛)、丙飛会が相当調べ上げているものの履歴までは完備していない。それより、困るのは操縦練習生、偵察練習生出身者である。「操練会」や「偵練会」というのは戦中も戦後も存在しなかったのだ。(プロ野球でも南海ホークスなど、OB会のない球団があるのに似ている)
特空会というのがあったが、これは搭乗員だけの会ではなかった。
それで、証言や書類、写真などの状況証拠を積み重ねてゆくしかないのだが、本来、国がやるべき操練、偵練の名簿作りを、個人でやっている人が身近なところにいる。寸暇を惜しんで辞令公報をメモしたり資料を当たったりという努力にはほんとうに頭が下がる。
いきなり話が変わるが、2009年、女優・森光子さんの舞台「放浪記」2000回記念のフジテレビの特番でお手伝いしたことがある。
森光子さんの人生をたどってゆく上で、戦時中の南方戦線の慰問巡業は外せない。そして、昭和52年、森さんが司会を務めていたNHK「第9回思い出のメロディー」(8月13日放送)で、戦地で慰問した将兵と再会するサプライズの設定で登場した、8名の元零戦搭乗員にインタビューしたいというのである。
登場したのは、二〇二空飛行隊長鈴木實中佐以下、分隊長塩水流俊夫大尉、普川秀夫、吉田勝義、八木隆次、増山正男、長谷川信市、大久保理蔵といった面々。
だが、2009年時点でご存命だったのは吉田飛曹長だけで、フジテレビのスタッフは吉田さんにインタビューし、その映像が番組でチラッと流れた。吉田さんも、戦歴ではなく森光子のことだけ聞かれることには面食らわれたに違いない。
それにしても、昭和52年にはこれだけの顔が揃ったというのは、まったく、時の流れの無情さを感じる。鈴木中佐と吉田飛曹長以外の方にはお会いする機会がなかったから、なおさらである。
これだけ名前を挙げても知っている人はそう多くないと思うが、皆さん、ダーウィン空襲でスピットファイアを圧倒し、その後トラック邀撃戦、ビアク攻撃などを潜り抜けた歴戦の勇士ばかりである。
操練33期のベテラン搭乗員、普川秀夫さんも、戦記にはまずお名前が出てこないが、昭和18年6月30日のブロックスクリーク空襲では指揮官鈴木少佐の第二小隊長を務めるなど、戦闘行動調書にはしばしば出撃記録が残っている。
こんな、知られざる搭乗員について、別のところからエピソードが拾えた時の喜びは筆舌に尽くしがたい。
海兵73期、三四三空戦闘四〇一飛行隊(極天隊)の外海信雄中尉の手記に、次のような記述がある。
『地上でこそ幅をきかしていたが、空中ではベテランの少尉、飛曹長には一目置かざるを得ない。単機同士でスタント(巴戦)をやると何時の間にか後にくっつかれる。
ある日松山上陸の帰りのバスのなかで、あとから乗ってきた眼光の鋭い少尉が上席に座ったのでその非礼を咎めたところ、じろりと我々を睨んで
「勝負しますか?」
その気迫に圧されて次の言葉がでなかったことがある。それが荒んでおり、若い実力のない中尉が何を言うかという気持ちもあったのだろう。』
・・・・・・ここで、気迫で若い中尉を黙らせてしまった特務士官のベテランの少尉こそが、普川さんである。こんなエピソードに出会うと、ああ、お会いできればよかったのになあ、と思うのだ。それにしても、こんなことを率直に書き残された外海さんも実にご立派であると思う。
戦後の消息を存じ上げないが、二〇二空でしばしば小隊長を務めた操練28期(同期には羽切松雄さんがいる)樽井亀三上飛曹も、いわゆる戦記本には出てこないがその豪傑ぶりが語り継がれていて、気になる人である。
『祖父たちの零戦』(講談社)で、編集の都合でカットしたなかに、次のような場面がある。
『二〇二空隊員の中には、遊郭で酒に酔い、女の態度に腹を立てて石灯籠を蹴り倒し、そこに駆けつけた憲兵を殴り、そんなことを繰り返して、同年兵がみな准士官の飛行兵曹長になっているのに進級が止められ下士官のままでいる樽井亀三上飛曹のような豪の者もいた。海軍の下士官兵の軍服右腕には、官職区別章(階級章)の上に「善行章」と呼ばれる「へ」の字型のマークが入っている。これは、大過なく勤めていれば三年に一線が付与され、海軍でのメシの数を示す目安でもあるが、不祥事を起こすと剥奪される。海軍に入って十年を超える樽井の軍服の右腕には、本来なら三本の善行章が輝いているはずのところ、一本しかついていなかった。
二〇二空の搭乗員は総じて気性が荒く、五十人以上が折り畳み式ベッドを並べる大部屋の搭乗員寝室では、
「ヤアヤア、遠からん者は音に聞け、近くば寄って目にも見よ、われこそは大日本帝国海軍の・・・・・・」
などと大声で寝言を言う者もいる。』
こんなエピソードを、一つ一つ丹念に拾っていく作業をしていると、たまに読む小説や映画の描写が薄っぺらく感じられて仕方がなかったりする。
さりとて、これをどのように体系化し、カタチとして作っていくか、それが難しい。
- 祖父たちの零戦 Zero Fighters of Our Grandfathers (講談社文庫)/講談社
![]()
- ¥830
- Amazon.co.jp
今冬、トレンチコートへの挑戦
最近行きつけになった、オーダーショップでは、一年前から
「今年、ハリスツイードのいいのがいっぱい入りますから」
と、私と同世代、トラッド命の店長が言う。
「ハリスツイード、いいねえ。黒に近いヘリンボーンのがあったら
「そうでしょ、そうでしょ。あと、こんなのでスリーピースはどう
「ほな、佐藤浩市に売られたら?僕はどちらかというと岡田准一な
「フランネルもいいのが入りますよ」
「黙って聞きなさい。フラノの紺のブレザーは毎年必ず新調してる
「最初っから欲しいものが決まってる人は、お薦めのし甲斐がない
「騙されないでしょ(笑)。服屋が何と言っても、好みのスタイル
……と、こんな感じ。
ところで、次の秋冬には、四半世紀越しのチャレンジをしようと思
それは、トレンチコート。
「カサブランカ」のハンフリー・ボガートに憧れて25歳の頃にブ
25年前当時のカタログによると、定価14万円。それを確か親し


だけど、当時の私は若すぎて、とてもトレンチコートの風格に太刀
だがこの夏、私は齢知命を迎える。いくらなんでも、トレンチコー
・・・・・・と思い、ちょっとひらめいてブルックス・ブラザーズ
50歳で、トレンチコートに初挑戦。さて、どうなるか。これの下
『祖父たちの零戦』(講談社文庫)、重版が決まりました。
拙著『祖父たちの零戦』(講談社文庫)、おかげさまにて発売後6
ご購入くださった皆様、有難うございました。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!

http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2775301
講談社BOOK倶楽部で、「もうひとつのあとがき」が読めます。
こちらもぜひ。
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bunko/afterword/page04.html
今年も海原会慰霊祭に行ってきました。
日本海海戦108年。
『祖父たちの零戦』(講談社文庫)さらに重版。
『祖父たちの零戦』(講談社文庫)、発売半月で3刷決定!
取材にご協力くださった方々への想いもあっ
皆様、ありがとうございます。
もちろん、まだまだ満足はできません。気を引き締めて謙虚に、さ
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2775301&x=B
大空を翔けた零戦飛行隊長のドキュメンタリー
この書は、一代の名機「零戦」に跨り、日本のために命を懸けて戦った、そんな名もなき男たちの鎮魂の書である――百田尚樹氏
ミノル、俺たちのやりたかったことはこんなことだったのかな――二十七機撃墜・味方損失ゼロ、奇跡の初空戦を指揮した進藤三郎。敗色濃い南太平洋でなおも完勝を続けた鈴木實。二人の飛行隊長の人生を縦糸に、元搭乗員一二四名への二〇〇〇時間インタビューを横糸に織り上げた、畢生(ひっせい)のノンフィクション!
※本書は2010年7月に講談社より刊行されました。文庫化にあたり、一部を加筆・修正しました。

ラバウルの友人・フレッドさんのこと。

農業研修で来日し、四国高松で1年4ヵ月暮らしたことが
とても勉強熱心で几帳面で、日本人的な気配りのできる、
一緒にいた5日間、彼はつねにノートと鉛筆を離さず、飛
「コレハナントイウヒコウキデスカ?」
とか、地元の人にも観光客にもほとんど顧みられない「小牧
「コノフネハ、ドンナフネデスカ?」
とか、その都度、私が日本語と英語と身振り手振りで説明

しまいには、零戦と九九艦爆と九七艦攻と一式陸攻、さら
「九七艦攻は何キロの爆弾が積めるでしょう」
「一式陸攻の乗員は何人ですか?」
「零戦二一型と三二型の違いは?」
・・・などにスラスラ答えられるようになり、彼は大得意
そして5週間後、NHKの撮影スタッフと俳優の染谷将太
今日、ディレクターの大島さんに聞いたところでは、私が
「ガイドの説明が長すぎる!ココポの戦争博物館の零戦の
と、苦情が出たという(笑)。

・・・・・・ごめんよ、フレッド。もっとかいつまんで、簡潔に説明す
そういうことに興味のない日本人観光客もいるんだよ、残
でも、また会いたいなあ!
筑波海軍航空隊
筑波空は、本部庁舎の建物が現存し、滑走路も生活道路として痕跡をとどめている。
自分のブログを振り返ってみたら、昨年6月2日、柳井さんの「お話会」があった。「お話会」と表現はぼかしたが、要は東宝スタジオで、今年12月公開の映画「永遠の0」の、「オールスタッフ」の顔合わせがあり、そこにお越しいただいたのだ。
山崎貴監督や主演の岡田准一さんが、食い入るような目でお話に聴き入っていたのを思い出す。
以下、昨年6月2日の記事。
神風特攻第六筑波隊・柳井少尉。
テーマ:ブログ
さて。今日は元零戦搭乗員・柳井和臣さんのお話会がある。

(昨年6月、NPO法人「零戦の会」主催「柳井さんを囲む会のときの一コマ)
柳井さんは山口県出身、慶応義塾大学在学中の昭和18年に文系学徒の徴兵猶予撤廃により12月海軍大竹海兵団に入団した後飛行予備学生(14期)に採用された。
19年2月から6月まで土浦海軍航空隊で搭乗員の基礎教育の後、出水海軍航空隊で操縦訓練を受け戦闘機専修となって筑波海軍航空隊に配属(筑波空が滑走路工事中のため、20年2月まで三沢基地で訓練)。
19年12月に少尉任官、翌20年2月に特攻隊員を志願して20年4月鹿児島県鹿屋基地に進出、七二一空戦闘三〇六飛行隊の所属となって20年5月14日第六筑波隊員として特攻出撃された。

このとき一緒に出撃した、隣の索敵コースの富安俊助中尉(予備学生13期)はエンタープライズに突入して大破させる戦果を挙げたものの、柳井少尉は予定針路に敵を見ず、反転帰投した。その後再出撃の機会なく、富高基地で終戦を迎える。
出水空時代に行われた軟式野球の試合では、プロ出身石丸進一投手(20年5月11日特攻戦死)や本田耕一一塁手(同5月14日特攻戦死)はじめ六大学リーグの選手たちと14期チームを組んで、「教官教員チーム」に大勝したこともあったとのこと。この他にも多彩なエピソードをお持ちである。
以下は、メモ書き。
・昭和19年12月、14期の戦闘機専修のうち120名が筑波海軍航空隊へ。滑走路の舗装工事中だったため三沢基地で離着陸訓練。
・昭和20年2月、滑走路の舗装のできた筑波空で「120名のうち50名の特攻隊員を募る」。普通の藁半紙に「望・否」(?)に○をつけ、官等級氏名を書く。2名(?)をのぞき志願。あくまで本人の意思とは言うものの、無言のプレッシャーを感じた。
・選ばれたものは、隊門すぐのところにある「神風舎」(じんぷうしゃ)と称する建物に入り、大部屋で起居。ガンルームとは別。以後、燃料の都合もあり、選ばれた者のみが飛行訓練を受ける。(20年3月1日をもって、特攻以外の飛行訓練がなくなる)
・特攻訓練は、滑走路または海面をめがけて急降下、高度2000~3000メートルから500メートルまで。角度は45度と言われたが、零戦はどうしても浮いてしまうので30度ぐらいの緩降下になってしまう。真っ逆さまに落ちるぐらいの感じで、タブで頭が下がるよう修正して最大角度で突っ込むと、ガソリンの臭いがプーンとした。引き起こすときは力が要るし、強いGがかかる。500で引き起こしても実際にはもう200ぐらい沈む。
・角度を下から教官が双眼鏡で見ていて、講評を受ける。標的については記憶にない。T字布板?
・筑波から富高に進出してから、飛行甲板を樹木で擬装した空母「海鷹」を目標に別府湾で襲撃訓練をやった。大分基地に着陸して講評を受けた。
・第四筑波隊までは、零戦二一型または練戦に乗って4月上旬に富高に進出。第五筑波隊以後はダグラスに乗って富高へ。ここで初めて、零戦五二型に乗ることになる。
・遺品整理、遺書を書くのはあらかじめ済ませてある。あとは出るとき、「今から出撃します」と書き添えるのみ。出る順番はだいたい決まっているが、いつ出るかはその時にならないとわからない。敵情、零戦の整備状況、天候、搭乗員の健康状態などで流動する。
・5月11日午後、整列、第五筑波隊鹿屋基地出撃。目標は沖縄本島沖の敵艦船。別盃あり。皆で帽を振って見送る。
・毎朝、朝礼があり、中島正中佐から、陸軍百式司偵の報告による敵情説明。海軍の偵察機でないのが奇異な感じがした。
・食事をするなど、ガンルームに相当するのは野里小学校、宿舎はそのすぐ横の横穴。照明は裸電球、虱多い。敵情が大丈夫そうなときは「飛行機を見に行く」と称して脱外出。
・5月13日、「11日の攻撃で撃ち漏らした敵KDB(機動部隊)北上中」との説明、夜、翌日早朝発進予定を告げられる。
・5月14日0300頃、洞窟の宿舎で起され、0400、野里小学校校庭に整列。搭乗割発表、敵情、攻撃法について細かい説明。別杯なし。
「出撃急ゲ」とのことで、搭乗員はトラックの荷台に乗ってめいめいの飛行機へ。飛行機は掩体に分散。滑走路南側の掩体の前に引き出された零戦は、整備員により試運転され出撃準備ができていた。零戦五二型に五十番搭載。0500頃出撃。見送りは整備員のみ。
・5月11日、14日の出撃は直掩・戦果確認機つかず。
・敵位置不正確のため索敵攻撃。4本の索敵線。柳井少尉は北端のライン。一時間飛んで、左に変針、15分飛んで、さらに左に変針。2機ずつの2組が一本の索敵線。2機は海面すれすれの低高度、2機は高度3000程度の中高度。計17機発進。ただ、列機との集合はできなかった。
・柳井少尉は敵艦を見ず、帰還。帰ってきたのは3機。柳井少尉は岡村司令から休暇が与えられ、トラックに乗って温泉で静養。
・この頃、筑波空から来た搭乗員は七二一空戦闘三〇六飛行隊に編入された。
・6月22日、沖縄が陥ち、筑波空組を中心に編制された「神雷爆戦隊」が最後の出撃。「(沖縄の)弔い合戦。沖縄へ行ってくれ」とのはっきりした訓示があった。
・沖縄失陥後は本土決戦に備え、鹿屋、富高の零戦を、松山基地等に空輸し、汽車で戻る日々が続いた。6月22日以後は、旧筑波隊の出撃はなかった。
・筑波空は、中野司令、横山飛行長が特攻に対し積極的な姿勢ではなく、同じ14期でも元山、谷田部に行った組より特攻に出るのは遅かったと思う。
昭和18年6月7日、第一次「ソ」作戦(ルッセル島航空撃滅戦)
六月六日、「ソ」作戦に向けて、二〇四空零戦三十二機がブインに、二五一空零戦四十機がブカ基地に進出した。五八二空零戦隊二十四機は、すでにブインで作戦中であった。
戦闘機だけで行くと敵機が邀撃に上がってこないので、宮野の発案で零戦の一部に爆装(六番―六十キロ爆弾二発)させ、艦爆を装って敵戦闘機を誘い出すことになった。しかし戦闘機に爆装することは、鈍重になる上に、爆弾投下後も爆弾架が空気抵抗となるので、非常に危険な任務である。しかし宮野は、自ら進んでこの役目を引き受けることになった。
宮野直率の二個小隊八機が爆装、敵機をおびき寄せて、残る戦闘機がそれを叩きつぶすという算段であった。爆装するのは、宮野小隊・二番機・辻野上上飛曹、三番機・大原二飛曹、四番機・柳谷二飛曹、二小隊一番機・日高義巳上飛曹、二番機・坪屋八郎一飛曹、三番機・山根亀治二飛曹、四番機・田中勝義二飛曹。
六月七日午前七時十五分、発進。総指揮官・進藤三郎少佐以下、五八二空二十一機、二五一空・向井大尉以下三十六機、二〇四空・宮野大尉以下二十四機、あわせて八十一機の大編隊は、空を圧して進んだ。この日は二〇四空のみが一個小隊四機編成をとり、五八二空、二五一空は三機編成のままである。在ラバウル・ブインの戦闘機隊搭乗員中、最先任である進藤少佐は、五八二空では飛行隊長であると同時に、司令の相談役のような立場にあって、よほど大きな作戦でなければ出撃することはなかったが、いざ出撃する時は、万が一にも総指揮官機が故障で引き返したりすることのないよう、乗機を入念に整備させた上に必ず予備機を用意して、出撃当日は朝早くから試飛行を行うことを常としていた。
「ルッセル島に向かって南から北へ、爆撃のために緩降下を開始した時、グラマンが二機、向かってくるのが見えました。私は三番機で隊長機の右後ろについているので、左側はよく見えています。逆に四番機の柳谷機は、右側を見ているから敵機は見えてない。隊長、早く爆弾落としてくれないかな、早く、早く・・・と思いながら、やっと投弾したその時、グラマンがダーッと頭上を通り過ぎ、見ると柳谷機が、グラッと傾いて墜ちて行きました」
柳谷二飛曹は、墜落状態の中で意識を取り戻した。破れた風防から風が轟々と入っていた。柳谷は無意識のうちに右手を伸ばして操縦桿を引こうとした。が、操縦桿がつかめない。見ると、右手の親指一本を残して、他の四本が吹き飛び、血がドクドクと噴き出していた。柳谷は左手で操縦桿を握ると、たくみに機を水平飛行に戻した。操縦席の中は、鮮血で真赤に染まっている。出血で、ともすれば意識が薄れていった。右手と右足には、重い鈍痛が広がっていた。そんな中、柳谷はどうにか、不時着場として使われているムンダの飛行場に着陸することができた。ああ、地面に着いたと思ったとたん、柳谷は意識を失った。
「ムンダには味方の陸戦隊がいて、気がついたときには、私は小屋の板の上に寝かされていました。そこで、このまま放置すると破傷風で生命が危ない、ということで、名も知らない軍医に、麻酔もかけないまま鋸で右手首を切断されました。暴れるといけないからと、三人の看護兵に押さえつけられ、口には脱脂綿を詰め込まれて、叫ぶこともできませんでした。手術が始まったとたん、ドンッと殴られるような激痛が体中を走りました・・・」
手首から先がなくなった右手にはグルグルと包帯が巻かれ、血と脂汗にまみれた柳谷は、ふたたび意識を失った。
柳谷機が編隊を離れた後も、空前の規模ともいえる激しい空戦が続いていた。この空戦の模様は、二五一空分隊長・大野竹好中尉の当時の手記と、二〇四空三中隊一小隊四番機・中澤政一二飛曹の日記でうかがい知ることができる。まずは大野中尉の手記から――。
「ルッセル島とその西北のブラク島の中間、高度六千メートルから海面に至るまで、恐るべき凄烈なる大空中戦が展開された。そして、我々は今やその巨大な闘争の、荒れ狂う旋風の真っ只中にいた。グラマンがいた。エアラコブラがいた。ボート・シコルスキー、ロッキード・ライトニング、カーチス・トマホーク、おおよそ航空雑誌に出るほどのアメリカの戦闘機のすべてが、総数百二十~百三十機あるいはそれ以上もいたであろうか、次々と雲霞の如く襲いかかってきた。
今や味方は顕著な四つのグループに分かれ、そのうち二つが最も激烈な死闘を続けていた。二〇四空の二十四機がルッセル島とイサベル島の中間海上で、我々二五一空の二中隊、三中隊の半数、四中隊がルッセル島とブラク島の中間海上で、そして二五一空残余の十二機が隊長・向井大尉の指揮下に、高度七千メートルでこれら死闘する味方の支援に任じ、五八二空の十数機は更に敵を求めて西方にあった。
敵は刻々数を増して、味方もようやく苦戦の色が見えてきた。深町二飛曹機はP-39一機を仕止めたが、食い下がった他の一機の猛射を浴びて自爆した。遠藤一飛曹はP-38を追い詰めて撃墜した瞬間、急を救わんとがむしゃらに前上方より襲いかかってきた敵P-39をかわし得ずと見るや、猛然体当たりを敢行、自らも微塵と砕けて散った」
次に中澤二飛曹の日記――。
「六月七日 ルッセル島航空撃滅戦(ソ作戦第一次)
予想通り邀撃に舞上がりたる敵G戦、P戦、ボ戦よりなる我々と同勢力の敵機群と遭遇、ルッセルの空を覆う大空中戦を展開す。
惨敗に屈せぬ敵は戦法を変えて、十機ぐらいずつの分散兵力にて、かつてなき苦戦となり。本隊のみにても、老練なる日高上飛曹を始め、山根二飛曹、岡崎一飛曹等歴戦の勇士が壮烈に戦死す。柳谷二飛曹に至りては降爆中前上方より右腕及び右足に炸裂弾命中、鮮血に座席を染めて左手にて着陸、右腕第一関節より切断するも、不屈の搭乗員魂により万死の中に一生を得て十五日無事に帰還す。我神田二飛曹とシコルスキー協同にて一機撃墜」
二〇四空は、空戦で十四機(うち不確実二)の撃墜を報じたが、中澤日記にもあるように、爆装隊の日高義巳上飛曹と山根亀治二飛曹(丙三期)が未帰還となり、岡崎靖一飛曹がおそらくF4Uとの空戦中に被弾、自爆戦死した。山根二飛曹は、六空第一陣でラバウルに進出したうちの一人で、これまでに三機撃墜の功があった。他に柳谷二飛曹が右手を失う重傷を負ったのは先述の通りである。これで、山本長官護衛の六機のうち三名が、一挙に欠けることとなった。爆撃のほうは、爆弾一発を飛行場至近に命中させたものの効果のほどは不明であった。
五八二空はグラマンF4F四機の撃墜を報じ、全機無事帰還。二五一空は合計二十三機(うち不確実五)の撃墜を報じたが、増田勘一二飛曹(乙十一期)、中島良生二飛曹(甲七期)、深町豊二飛曹(丙七期)が自爆、遠藤枡秋一飛曹(乙九期)、松吉節二飛曹(丙三期)、関口俊太郎二飛曹(甲七期)が未帰還と、計六名の戦死者を出している。その他四機が被弾、向井大尉はP-38に撃たれて燃料タンクに被弾、不時着水している。
日本側の戦果を集計すると、撃墜は四十一機(うち不確実七)にのぼり、わが方の自爆・未帰還も九機を数えた。行動評点は、二〇四空・B、五八二空・C、二五一空・Aであった。連合軍側の記録では、百十機の戦闘機で邀撃し、零戦二十四機を撃墜、七機を失ったと述べている。
南東方面艦隊兼第十一航空艦隊航空甲参謀、三代一就中佐の回想によると、この日、クラスメートの二五一空司令小園安名中佐から、
「おい三代、ラバウルへ出てきたら最後、生きて帰る搭乗員がいないというのでは士気に影響すると思う。宮野なんかは、もう帰していいんじゃないか」
と意見され、開戦以来前線に出ずっぱりの宮野大尉の経歴を思い、もっともと思い、宮野の転勤の手続きをとったという。十一航艦司令部が内地転勤の「手続きを取った」からには、宮野には近日中に次の任地が言い渡されるはずであった。















